裁判所事務菅になるためには?
裁判所事務官になるには、大学院、大学もしくは高校卒業後、裁判所事務官採用試験を受けて合格する必要があります。
同試験は総合職試験と一般職試験があり、いずれも30歳未満という年齢制限があります。
総合職試験の場合、院卒者試験と大卒程度試験に分かれており、専門知識を問う筆記試験や人物試験、個別面談等さまざまな角度から合否が判断されます。
学部法律の知識が問われるため、やはり傾向として法学系学部の出身者が多くなっています。
試験の種類
最高裁がこれらの者と同等の資格があると認める者で、高卒者試験もあります。.高卒見込み及び卒業後2年以内の者。
(中学卒業後2年以上5年未満の者も受験可)です。
この試験(院卒者・大卒程度・高卒者試験)を受けられない者は国家公務員法第38条の規定に該当する者、成年被後見人又は被保佐人、禁錮以上の刑に処せられたもの、試験内容は総合職試験/院卒者試験に分かれています。
1次試験―2時試験
基礎能力試験(多肢選択式/30題:2時間20分)知能分野(27題)で①文章理解、②課題処理、③数的推理、④資料解釈と分かれています。
知識分野は専門試験(多肢選択式:30題)になります。必須問題は中心的に憲法、民法になりますのでご確認ください。
基準点(最低限必要な得点)は、原則として満点の30%で、成績上位者より合格ですので、かなり難易度が高い資格で、十分に勉強する必要があります。
最終的には面接もあります。
勉強方法は
裁判所事務官は、各裁判所の裁判部や、事務局に配属されるため六法全書を持って勉強する必要があります。
日ごろから自分の「考える力」を養うことも大切です。
面接では裁判官になるための常識を問うことになります。
裁判所事務官として具体的にどんな仕事をしたいのかをしっかり明白にすることなど答えられるようにしておきましょう。
免除(科目等)について総合職試験(院卒者試験/大卒程度試験、法律・経済区分)の特例制度について十分な成果を得る事が出来ます。
受験する際には多くの情報を最高裁判所のホームページで確認することが出来ますので、しっかりと確認しておきましょう。
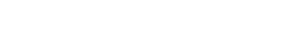

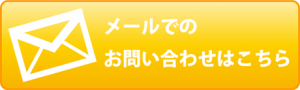
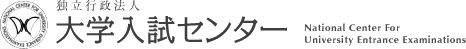
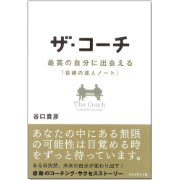
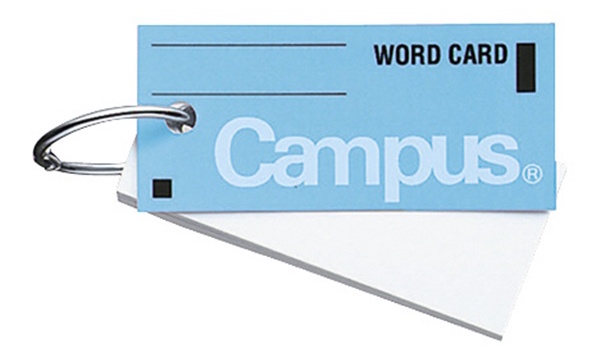
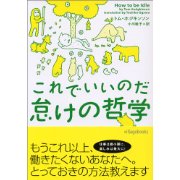
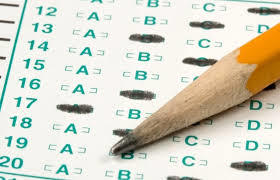


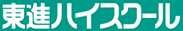

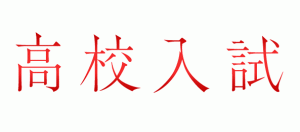

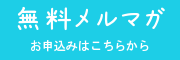
コメントする